【昇格試験対策】 後輩の論文を添削してみた(前編) – 高い点をとるためには〇〇を知ること! – | 論文指導内容も公開
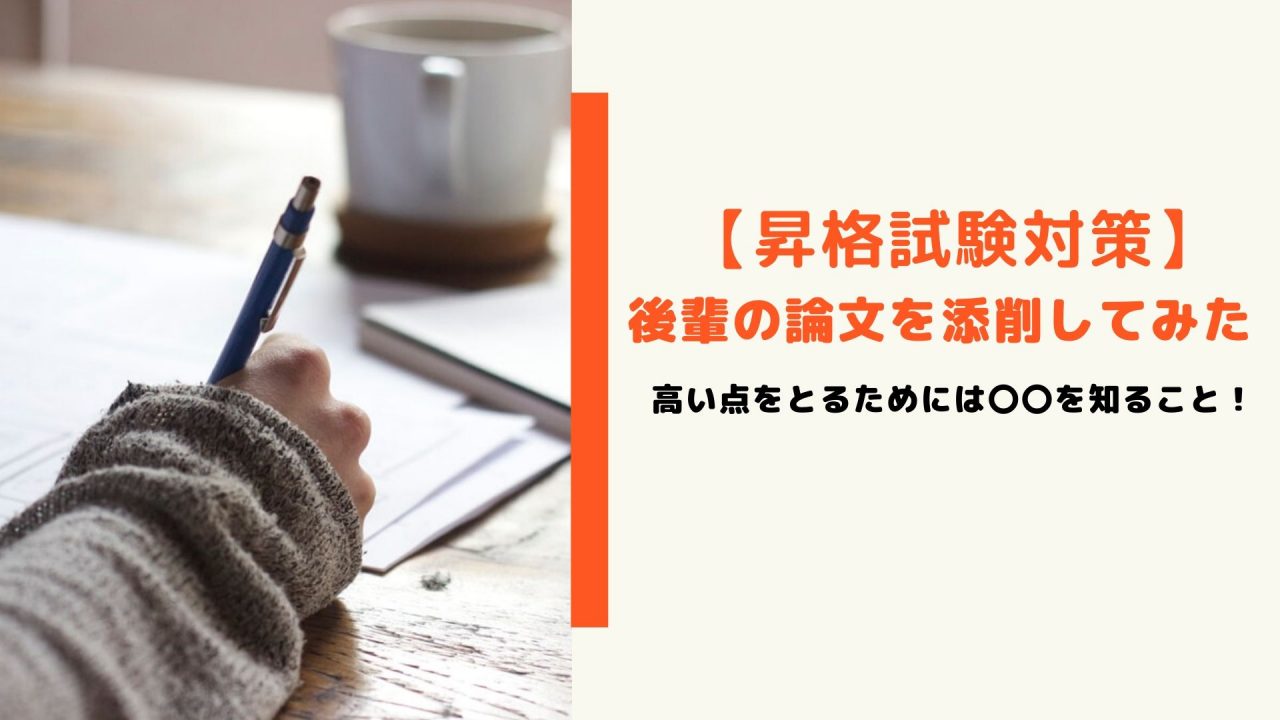
この記事では、実話に基づいて昇格試験の論文で手っ取り早く高い点をとる秘訣を紹介します。また、実際の論文指導内容も公開しています。
これを読んで悲報を聞かないで済む人が増えれば良いなと思い、後輩の論文添削を題材にして、ストーリー化してみました。
・スカハン先輩
某製造メーカーに勤める中堅社員。当時、論文(ライティング)には自信があったが、昇格試験前に部長に見せたら「これじゃ全然ダメ。出題の意図が全く分かってない」と言われ、落ち込む。その後、部長の指導やヒアリングを通して、自分なりに受かるポイントを分析して、無事合格。
・マジメ後輩
スカハンの会社の後輩で、社内プロジェクトでもたまに一緒になる。そしてお酒もスキで仕事終わりに飲みにいったりもするくらい仲が良い
マジメ後輩は今、△〇×システムを開発する部署にいて、○○機の◎◎を向上させる仕事をしている。今年ついに昇格試験を受けるそうだ。
序章
ある日、スカハン先輩のところに会社のマジメ後輩からこういうLINEが来た。

スカハン先輩は、自分も苦労して試験に受かった方なので二つ返事でOKを出した。
さっそく次の土曜日に後輩宅にお邪魔して、論文を見てあげることにしました。

努力家のマジメ後輩なので「結構良い線いってるだろう」と思って、スカハン先輩は軽く粗探ししてやろうくらいの気持ちで読んでいました。
しかし、マジメ後輩の論文を読み終わったスカハン先輩の顔はやや怪訝。
マジメ後輩、大いに勘違いするの巻

単刀直入に言うと、これじゃ試験は落ちるな。具体的にどこが悪いのかを説明する前に、一番大事な事を教えておくよ。昇格試験で一番大事な事は、出された問題に答える事ではないんだよ。






「あなたが行なっているコスト削減を定量的に説明しなさい」
だったら、正直いってマジメ後輩の仕事内容では1行も書けないと思う。でもね、試験に点をつけている人は、マジメ後輩がどんなコスト削減をしているかなんて興味ないんだよ。この設問に対してどういう文章を書くかを知りたいだけなんだ。だからいきなり嘘を書いて
「私は▲▲ソフトの各バージョンを統合する事で〇〇人月/年の工数削減に寄与しました」
って書いて良いわけよ。


「システムを統合して、コスト削減に寄与するとともに部門間のコミュニケーションをスムーズにできるようにした。」
なんて書いても採点官は「定量的にって聞いているのにちゃんと答えてないな」ということで、即!没!さよなら!やね。






昇格試験で書く論文というのは、君の能力を確かめるためのテストであって、君が何をしているかを確かめるテストではないんだよ。
俺は、添削してくれた部長や実際の採点官との会話でこのことを知ったんだ。
じゃあ、ここからは秘策を伝授しよう。もし君が大学受験のテストを受けると仮定して、受験前に正解が見られたら、絶対合格できるでしょ?
昇格試験の論文も同じ!もちろん論文には絶対的な「答え」はないから、そのままは上手くはいかない。でも「答え」に近いものに「採点基準」というものがある。
それが分かっているなら、高得点が取れるように、そして減点されないように、論文を書けばいいよね。
つまり高い点をとるためにまずしなくてはならないのは「論文を書く」 ことではなくて、「採点基準を知る」っていうことなんだよ。


まぁいいや。採点官はというのは、実は論文を評価するわけじゃないんだよ


1. 問題を正しく理解する能力があるか
2. 論理的な説明をする能力があるか
つまり論文試験というのは、あなたにある問題を論理的に整理する能力があるかどうかを確認する試験でもあるのです。
したがって、「自分はその能力があるぞ!」とアピールしないと高い点はとれません。



いよいよ採点基準だ。いろいろあるんだろうけど、もっとも大事なものは次の2つだ。
1. 設問の要点を正確に把握して、その全てに正確に答えているか。
2. その答え方の論理展開(ストーリー)が正しく、しっかりしているか。
だよ。とくに 1. ははずしたら即落第やね。

マジメ後輩、ボロボロの巻

マジメ後輩の論文のどこがまずいか一つ一つ教えてあげよう。まず、今回の論文問題はこれだね。
企業を取り巻く社会的および技術的環境は、かつて無いスピードで変革しており、変革をキャッチし迅速に対応することの重要性が高まっています。この点に関する、職場における課題をあげ、あなた自身が日常の業務を通してどの様に対処しようとしているか、考えを述べなさい。

・背景 :
企業をとり巻く社会的技術的環境がハイスピードで変化しており、その変革をキャッチし迅速に対応する重要性が高まっている。
・質問 :
①「変革をキャッチし、迅速に対応する」ことに関する自分の職場での課題
② その課題を自分の業務でどのように対処しようとしているか





ということで、下記のファイルが指導した内容です。



LINEの友達追加で上記の論文指導内容をプレゼントします!
「後輩の論文指導」とメッセージしてください。
![]()


「良い△△システムを作るための課題と改善策」
としては、めちゃくちゃ良い論文なんだけど、
「変革をキャッチし迅速に対応するための課題と対処法」
の論文になっていないんよ。


いずれにしても問題文章の分析が甘いね。


スカハン先輩ならこう書く!
背景を論じる(題意を肯定する)



いきなり質問の答えを考える前に、背景をどのような観点でとらえるかを考える必要がある。ただ単に質問に正確に答えるだけではきっと合格点はもらえないと思うな。
その答えが、ちゃんと「背景」にかなったものである必要があると思う。それから、こういった「背景」っていうものは、個々の技術分野とは違って、「経営」とか「利益」とかに繋がる要素が含まれていることが多いんだ。採点官は少なくとも部長以上くらいだろうから、下っ端の「技術」よりそういう話題が好きなんだよ。
何故なら、これから会社を担う存在として、昇格させるべきか否かを見極めるための試験でもあるからね。
読んでいて「うん、こいつは視野が広い!」って思われるのは得だと思う。で背景の捉え方なんだけど、大抵問題文の「背景」は抽象的な書き方をしているので、とらえ方が色々できるようになってるもんなんだ。だからこのあとで考える「質問の答え」を出しやすいように自分で都合良く定義してしまえばいいんだよ。ただし不自然なこじつけはNG。
設問の表現を素直にとらえて答に結び付くように決めることが肝心だね。
・企業を取り巻くハイスピードな社会的環境変革として、どの企業でもさらなる業務の効率化が急速に求められている
・企業を取り巻くハイスピードな技術的環境変革として、ソフトウェハの世界ではシステム化・統合化が求められ、それを支えるインフラも急展開で整いつつある。
・そのような背景を自分は(この論文は)どのように評価するか。このような分野での変革は、メーカーとしては追従すべき変化としてとらえるのではなく、ビジネスチャンスとしてより一歩前にでたとらえ方をする必要があると思う。
※すなわち、今までの個別の製品のシステム化・統合化を積極的に進め業務の効率化を必要としている市場に受け入れられるものを作る必要である。
※そういう点で、私が従事している○○という製品はシステム化を進める上で格好の製品であるが、実際にはそうなっていない。


いて気味悪いかも知れない。ちょっと分からないな。さて、それで、このように問題を整理する際には
・なになにについて、……どうである
・なになにについて、……どうする
と言う風にしておく方が良いと思うよ。実際に文章にする際に論点が明確になって歯切れの良い論文になるから。
それとここで重要なのは、※※ をつけたところだよ。背景について述べると、大抵夢物語になっちゃうんだけど、そのままじゃこれから書く「自分の職場での課題」に繋がらないでしょ。この部分の文章でそれを順々に自分の答えたい領域の話題に移していっているんだ。
質問の答えを決める

1.) 質問①、質問②の回答を漏れなく書く(1つでも抜けたらアウト)
2.) 背景の論じ方と整合をとる
特に 1.)は注意が必要だね。例えば「課題」を列挙してもそれが、「自分の職場」のものでなく一般的な課題だったり、自分がやっている仕事と関係はあるが、「変革をキャッチし、素早く対処する」事に関係しないものだったりすると駄目だね。後は、くだらないようだけど語尾のですます調どちらにするか、とかも注意して。
続きは後日
ここまで読んで「あぁ!そういう事か」と分かった方は、当初の僕よりも論文を書ける方だと思います。
もし、まだ先が見たい!と言う方は・・・後日続きを書くのでこのページをブックマークしておいてください(笑)
とりあえず、そんなの待っていられないという方は、こちらの本をお勧めします。
「全試験対応! 直前でも一発合格! 」
(2026/01/20 03:26:57時点 楽天市場調べ-詳細)
この本は、ポイントがしっかりまとまっており、例文もたくさん載せられているため非常にわかりやすいです。
本ブログで書いていることも一見すると「そりゃそうだ、当たり前だ」と思う事も多々あったかもしれませんが・・・
実際に自分で書いてみるとよく分からないことも多いと思います。
そんな時、この本でポイントと例文を確認できるので大変助かります。

2020年9月11日更新 NEW
と言う事で、待望の(?)後編ができました!
お時間ある方はこちらもご覧ください!
実際の論文の書き方例も紹介しています!

まとめ
と言う事で、実際の体験談をストーリー化してみました。
おそらくここで実践していることを本番でもできれば合格できると思います。
繰り返しですが、昇格試験における論文は
1. 人の書いた文章を正しく理解する能力
2. 論理的な説明をする能力
が見られています(と思っています)。
もし、これらの能力があったとしても、たまに採点官に読解力が無いケースもあります。
つまり・・・運も必要です(笑)
では、これから試験がある方、頑張ってください!

Roots Lab.では定期的にイベントを開催しています。興味のあるテーマがあればぜひご参加ください!

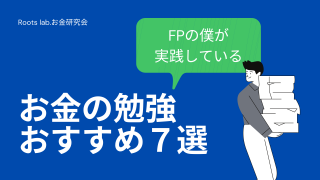





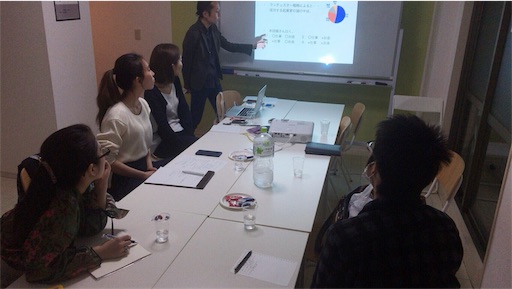

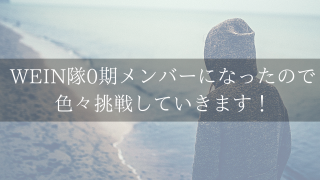

解説が分かりすく大変参考になりありがとうございます。
「質問の答えを決める」段にて
① Q1, Q2 の両方とも答える
② 質問①②の回答を漏れなく書く(1つでも抜けたらアウト)
とありますがQ1,Q2は質問①②と同意でしょうか?
また、「① は当然だけど、②は特に注意。」は「質問の答えを決める」段の①②の意と読み取ればいいのでしょうか?
理解を深めたくご回答いただけますと幸甚です。
ご質問ありがとうございます。
>とありますがQ1,Q2は質問①②と同意でしょうか?
はい、ご認識のとおりです。
少し表現が分かり辛かったので、以下のように書き換えました。
—
① Q1, Q2 の両方とも答える
② 質問①②の回答を漏れなく書く(1つでも抜けたらアウト)
↓
1.) 質問①、質問②の回答を漏れなく書く(1つでも抜けたらアウト)
—
また不明な点があればご連絡ください!
練習論文を上司や先輩に読んでもらうのですが取り組みがインパクトがない(ありきたり)と言われます。
何をどうしたらインパクトのある取り組みがかけるのでしょうか?
コメントありがとうございます。恐らくカメラ小僧さんが書いている論文は、今あなたが取り組んでることをそのまま事実として書いているのではないでしょうか?
昇格試験は一つ高い視座に立って書かなくてはなりません。
したがって今カメラ小僧さんが関わっている仕事において、先輩やリーダーがやっている取りまとめ業務を「あたかも自分がやっている」ことのように書くと良いと思います