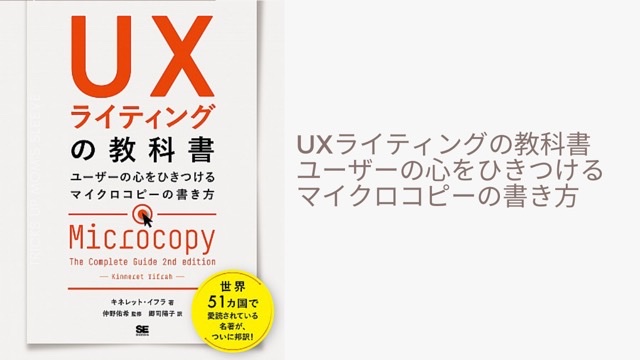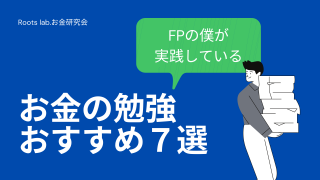この記事は「UXライティングの教科書 ユーザーの心をひきつけるマイクロコピーの書き方」のレビュー記事です。
・UXライターとしてワーディングを考えている人
・プロダクトマネージャー
・デジタルプロダクトのライター
・Webデザイナーとしてマイクロコピーを書く人
僕はUXライターとして色んなアプリの開発に携わっていますが、今までなかなかUXライティングについて体系的学ぶ書籍と出会えませんでした。
そんな時に今回たまたま見つけたのが、今回ご紹介する
「UXライティングの教科書 ユーザーの心をひきつけるマイクロコピーの書き方」です。
ボタン上の文字やフォーム、 エラーメッセージ、写真キャプションなど、ユーザーの行動を促す短い文言(非常に細部の箇所のコピー)のこと。一見すると目立たないが、ユーザー体験をより素晴らしいものにするために重要な役割を持つ。
また、最近ではメルマガやSNS(Facebook、Twitter、Instagram)の投稿などで、短い文章を書く機会も増えていますよね。
特にビジネスでSNSを活用している方にとっては、ユーザーや顧客に行動してもらいたいときこそ「マイクロコピー」が効果を発揮します。。
この本の内容について
本書は、主にマイクロコピーについて書かれおり、Webライターだけでなく、UX/UIデザイナーやマーケティング担当者、プロジェクトマネージャー、経営者など、Webに携わるすべての人にとって必携の一冊です。
「マイクロコピー」とは、デジタルプロダクトにおけるボタンやフォーム、アドバイス、エラーメッセージなどのテキストのことです。
本書を読むことで、わずかなマイクロコピーがユーザーにとって有益であることを学ぶことができます。これにより、ユーザーの行動意欲を高め、エンゲージメントを強化することができます。
このことからも、アプリ開発者だけで無く、プロジェクトマネージャーや経営層に近い方にも必須のスキルであると言うことが分かります。
目次
続いて目次を見てみます。
はじめに:マイクロコピーとは何か
Part 1:ボイス&トーン
第1章 ボイス&トーンのデザイン
第2章 会話体ライティング
第3章 モチベーションを高めるマイクロコピー
Part 2:エクスペリエンスとエンゲージメント
第4章 会員登録、ログイン、パスワードの復元
第5章 メールマガジンの配信登録
第6章 お問い合わせ
第7章 エラーメッセージ
第8章 成功メッセージ
第9章 エンプティステート
第10章 プレースホルダー
第11章 ボタン
第12章 404エラー
第13章 待ち時間
Part 3:ユーザビリティ
第14章 マイクロコピーとユーザビリティ:基本原則
第15章 疑問に答え、知識のギャップを埋める
第16章 不安や懸念を軽減する
第17章 エラーやトラブルを防止する
第18章 マイクロコピーとアクセシビリティ
第19章 複雑なシステムのためのマイクロコピー
目次を見る限り、特にアプリやWebサービスを開発してる人にとっては「あー、それだ!それが知りたいんだ!」と痒いところに手が届くラインナップになっているのではないでしょうか?
僕も手に取った時、思わず
「そうそう、エラーメッセージって、どう書けば伝わりやすいんだ?」
「設定成功した時のフィードバックってどんな感じで出すべきだろう」
など、気になる内容がたくさんあったので、ソッコーで該当ページを読破しました。
口コミ
SNS上での反応を見てみましょう。
UXライティングの教科書はもう少し具体的に書けたんじゃないのかなあという本でした。
機能じゃなくて、享受した後のメリットや価値を伝えよう。など勉強にはなるけど、ちゃんとやろうとすると不十分でこのままの知識で現場行っても“細かい人“になりそう
ブランドマーケ学んだ方が深く行ける気がした
— カイクン – BONO(ボノ) (@takumii_kai) March 13, 2021
有意義タイムでした、『UXライティングの教科書』おすすめです🙌 https://t.co/zFV8VmIorn
— mewmo (@mewmoppel) March 12, 2021
Web制作のクオリティを上げたくて「UXライティングの教科書」を買ってみたら想像以上に良書すぎました。
マイクロコピーの書き方をブランド分析まで落とし込んで言語化してくれているんですが、全271ページ中最初の63ページまではサイト制作だけじゃなくSNSにも転用できる内容です。 pic.twitter.com/dihZyRucWx
— ティーノ (@tyno_tyno_t) March 6, 2021
割と好評のようです。
結論
続いて、僕の個人的な感想です。SNSの口コミと同じような感想にはなりますが、非常に良書だと思います。
今UXライターとして働いている人はもちろん、コピーライターやテクニカルライターなどユーザーとのインターフェースを設計してある人全てに読んで欲しい1冊です。
今までこれほどUXライティングについて体系的に学べる書籍はなかったと思います。
と言うところで、ここからは僕が特に役に立った内容をいくつかお伝えしします。
内容
モチベーションを高めるマイクロコピー
私たちは、SNSの投稿やWebサイトを見た時、自分にとって価値のある物かどうかを瞬時に判断しています。
裏を返せば、仮にあなたがSNSの投稿者やWebサイトの運営者であれば、数秒のうちにそこから離脱させないように、確実に価値を認識してもらう必要があるのです。
そのためには、あらゆる言葉があくまでもシンプルで、明快で、なおかつ説得力を備えていなければなりません。
とにかく分かり易く、そして要点を伝えましょう。
コツは、ユーザーが利益を得るために必要な手順や方法を伝えるのではなく、ユーザーが何を得るかをテーマとして書けば良いのです。
×:正しい財産管理のための多彩なツール
〇:債務ときっぱり決別しましょう
〇:債務に最後のお別れを
×:中古車の新しい購入方法
〇:次の車を買いましょう、この方法なら安心です
〇:中古車購入―面倒な手続きはゼロ、保証は万全
ユーザーが何を得ることができるか・・・それを考えるためにも、まず自問しましょう。
あなたのプロダクトまたはサービスを利用した人々に、どんな変化が起こるか?
かつてはできなかったどんなことができるようになるか?
あなたが彼らのために解決できる問題は何か?
そしてそれを伝えます。
エラーメッセージ
エラーメッセージと言えば、そう。僕たちが書くテキストの中でも最も読まれたくないメッセージですよね。
そうは言っても、避けては通れないものでもあるので、エラーメッセージとは慎重に選び、ユーザーに確実な解決策を提示させなければなりません。
そんなエラーメッセージに言及するような書籍ってありそうであまりないですよね?
本書では様々なサービス(企業)の例を交えて、エラーメッセージについてのライティング手法を教えてくれています。
まず本書によると、エラーメッセージには大きく3つの役割があります。
1. 問題が発生した事実とその問題の性質を、簡潔に分かり易く説明する。
2. 解決策を提示し、ユーザーがすぐに戻って操作を完了できるようにする。
3. 操作の遅れをできるだけ好ましい経験に変える
なるほど。①、②については基本思想として念頭に置いていましたが、③についてはあまり考えた事がありませんでした。
エラーメッセージは、基本的に技術的な問題点をクリアするために文面を分かり易くかつ具体的に表現することが大切です。
したがって、汎用性の高いエラーメッセージは有用性が低いです。
エラーが表示されている状況では、ユーザーは操作が滞っている状態にあり、また不快な思いをしている状況でもあります。
だからこそ、できるだけ人間的な言葉でメッセージを紡ぎ、不快感を緩和させる表現を用いなければなりません。
そのためにも、UXライターの僕たちは次のようなことを確認しておく必要があります。
① エラーが発生した時に、ユーザーは何をしようとしたか
② システムはなぜエラーという反応を示したか
③ ユーザーが何をすれば操作を続行し完了できるか
④ 解決策が無い場合、別の選択肢をユーザーに提供できるか
④については、サポートセンターに問い合わせたり、OSやデバイスのアップデートなどの代替手段も記載する必要があります。
また、できる限り人間らしくサービス志向でライティングするという事も大切な要素です。
本書では、例としてPinterestやTescoなどのエラーメッセージが記載されていました。
例えば、
「ユーザー名またはパスワードが間違っています」
というエラーについて、以下のように紹介されています。
・Pinterest
おや?正しいメールアドレスが行方をくらましましたね、またはパスワードが違います。リセットしますか?
・Tesco
残念ながら、これらの詳細情報を認識することができません。もう一度お試しください。
ただし、こうした遊び心はブランドボイスに合っているかどうかも重要です。ブランドボイスに合っているのであれば有効ですが、伝統を重んじるタイプのブランドでは逆効果です。
ユーモアを使えないブランドの場合は、何ができないかではなく何ができるかだけを伝え、否定的なエクスペリエンスを提供しなければOKでしょう。
エンプティステート(空の状態)
エンプティステートとは、表示すべき情報が何もない状態の事です。
・良質なサービスを提供する事
・ユーザーに次の行動を指し示し、本来の目的に立ち返ってもらう事
例えば、検索結果が何も得られなかった時に表示される画面などを指します。
 Googleの検索結果が無い場合の画面
Googleの検索結果が無い場合の画面上記のGoogleの例を見て分かるように、エンプティ―ステート画面では、
・ここには何があれば良かったか
・ユーザーはここで何を得られたか
・状況を動かすためにユーザーができる事は何か
などを載せる必要があります。
もしまだ使われていない機能があれば、そのベネフィットを伝えて、使ってみるように勧めるチャンスです。
例えばECサイトなどであれば”カートが空っぽ”の状態であれば購入を勧めましょう。また、検索結果が何もない場合は、他の選択肢を提示するのも有効だと思います。
まとめ
ここ数年で一気に注目を浴びるようになったUXライティング。ただ、まだまだ紹介事例が少ない分野でもあります。本書では、ビジネスにUXライティングを取り入れ、成功を収めている事例が多数紹介されています。
英語をベースに訳されたものなので「ん?」と思ってしまう部分もありますが、視野が広がりライティング力が増す事は間違いないでしょう。
ぜひ、UXライティングの初心者の方はそばに置いておきたい!そんな1冊です。
Roots Lab.では定期的にイベントを開催しています。興味のあるテーマがあればぜひご参加ください!